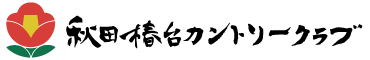秋田魁新報掲載記事(昭和55年12月19日)
南と北、そして由利海岸の三方から仙台・庄内・南部に攻め込まれた秋田の戊辰戦争は、久保田藩諸隊と援軍各隊の最後の踏ん張りで終わった。もっとも、反攻が功を奏したのではなく、薩長に対抗しようとした奥羽列藩同盟の各藩が崩れ、明治新政府に続々と帰順したことで終局した。だが、終わってみると、久保田領内の三分の二と本荘領、矢島領、仁賀保領、亀田領のほとんどは焼土と化していた。藩庁には膨大な借金が残り、この戦争に「ご一新」を期待していた領民の夢は、薩長中心の官僚政治の前にもろくも消えた。明治維新とは、そして「一藩勤王」を叫んで領内を荒廃させた戊辰戦争とは、秋田にとってなんだったのだろうか。狂気に始まり、失意のうちに終わった戦争の残したもののいくつかを列記し、しめくくりとしたい。
多くの血流し新政府発足 -戦死-
戦闘員として戦場を駆け回った隊士たちは、銃火や砲声の中で当然死と背中合わせの2ヶ月だった。秋田関係の各藩の戦死、負傷者、そして焼失家屋は別表に示したが、いずれも正確な数字ではない。「戊辰秋田藩戦記」や本荘、矢島、亀田、仁賀保の各藩記録から拾ったもので、これ以外に残されたものもないことから、現在では確かめようがない。
このうち、久保田藩の出兵、戦死、負傷者は、明治2年(1867)6月、藩庁が新政府軍務局に届けた数字。「秋田沿革史大成」には、戦死はこれより55人多い384人となっている。報告後、戦傷がもとで戦死した隊士たちをも「戦死者」として加えたか、あるいは軍役に動員した農兵、町人も含めたものだろうか。
焼失家屋は、侍屋敷、町家のいわゆる住居の分だけ。小屋や土蔵、寺院、神社などを加えれば8千戸を超えると推定される。横手城、本荘城のように自焼の例はあるが、焼失のほとんどは、侵入した仙台、庄内、南部の各隊の焼き打ちである。「秋田文化史年表」(原 武男編)によると明治元年の秋田の(由利を含む)人口は431,898人。一家6~7人平均と推察して7万戸前後。その一割が焼失した計算になる。
ちなみに、鳥羽・伏見から函館までの戊辰戦争全体で新政府軍の出兵は約12万人、戦死3,556人、負傷3,804人。抵抗した旧幕派諸藩の戦死はわかっているだけで4,707人、負傷は1,518人。逃亡が続出し、そのまま不明の者も多いので、確かな数はわからない。これらの数字は26年後の日清戦争を超えている。その時の日本陸軍は12万人、戦死は5,417人。明治新政府は、戊辰戦争でいかに多くの血を流した末にスタートしたかがうかがえる。
戊辰戦争の犠牲
| 藩 名 | 出兵数 | 戦死 | 負傷者 | 焼失家屋 |
|---|---|---|---|---|
| 久保田 | 8,696人 | 329人 | 316人 | 4,68軒 |
| 本 荘 | 600人(推定) | 13人 | 12人 | 770軒 |
| 矢 島 | 354人(農兵含む) | 8人 | 不明 | 319軒 |
| 仁賀保 | 80人 | 1人 | 3人 | 251軒 |
| 亀 田 | 600人(推定) | 8人 | 23人 | 不明 |
| 計 | 10,330人 | 359人 | 354人 | 6,024軒 |
多くの血流し新政府発足 -援軍-
戦争の末期で勝利を得たのは久保田藩各隊の危機感と士気の高まりにもよるが、西国諸藩や近隣からの援軍と新装備だった。総督府の諸藩援軍到着日録を追ってみる。いずれも慶応4年の分である。
▽5月9日=沢副総督と随従諸藩695人。
▽7月6日=鍋島援兵250人、土崎上陸。
▽7月23日=長崎振遠隊500人、男鹿江川(天王町)着。
▽7月24日=津軽援兵180人着(このほか7月29日に津軽四小隊着とあるが、いずれも到着地不明。9月5日には250人が花岡着)
▽8月15日=大村隊119人、島原隊200人、平戸隊200人着(到着地はないが、船川か土崎に上陸)
このあと8月18日には薩摩隊、肥前隊の1,700人が土崎に上陸し、最大の援軍となる。そして9月24日の雲州隊450人船川上陸まで、13回にわたり総計6,394人と記録されている。ただし、陸路からの援軍に不明の分があり、全体では久保田藩出兵8,696人と匹敵する8千人近くが秋田に来たようだ。後に四代目県知事として秋田に赴任する石田英吉(高知県出身)は、長崎振遠隊の一人として県南を転戦した。
海路をたどり、船川や土崎港に上陸した援兵たちは各寺院に一泊したあと戦場へ散ってゆく。当時、土崎港ではこんな唄(うた)が流行したという。
〽一夜泊まりのダンブクロに惚れて あすはジャチャラガチャラ 泣き別れ
これら援軍の戦死は、新庄藩の49人を最高に、薩摩隊42人、筑前隊33人、佐土原隊30人、長州隊21人など総計247人。秋田戦記から拾った数字だ。秋田市八橋の全良寺に「官軍墓地」(秋田市史跡指定)として埋葬されている。

多くの血流し新政府発足 -装備-
戦争の初期、久保田藩諸隊の意気が上がらなかったのは装備が劣っていたためとされているが、ではどの程度のものだったのか。
官軍(新政府軍)といえばダンブクロ姿に錦(にしき)の御旗、鉄砲かついでが普通だったこの時代、久保田藩のほとんどは甲冑(かっちゅう)に弓矢、旗差し物、槍(やり)と戦国期さながらの姿だったという記録がある。鉄砲ぐらいはあったろうが、「治にいて乱を忘れず」は昔語り。風雲急の世相にピンとこない家臣が多かったのだろう。いざ鎌倉となって大あわてで先祖伝来の武具をとり出し、中には城内の御兵具蔵から借り出した者もいたという。
由利口で1隊を率いた荒川久太郎が砲術所総裁の須田盛貞に、戦場から出した手紙が残っている。
「小銃1丁につき1日16発ずつ10日分の配給となっているが、その日の戦闘によっては50発も撃つ。とても足りないから、さらに1丁につき160発ずつ欲しい。十分な戦闘ができるには、1丁で320発あればいいと思う」
だが、補給しようにも藩庁の台所は火の車。銃なし弾丸なしで初戦から敗走を重ねた。
新式の洋式銃が行き渡るのは、戦争も終局近くになってから。椿台決戦の直前、イギリスの商人から小銃5千丁、弾丸10万発を購入した時、次のような二説が残っている。一つは、イギリス商人が庄内藩の注文を受け、松前から船で酒田に運ぼうとして土崎に寄港したのを久保田藩側が知り、一丁目川反の医者篠木隆司静斉を交渉役として横取りしたというもの。篠木は蘭学をかじったことがあり、横文字が少しできたという。
異説は、イギリス商人が売り込みに来て、連戦連敗の秋田方の足元を見てから「いらないなら庄内へ行く」と言ったため、やむなく買った。実際の戦闘で威力は発揮したが、実はイギリスの旧式廃銃だったという落ちまでついている。
後に家老小野岡義礼が篠木静斉のために周旋人として功労申請しているのを見ると、前者の説が正しいようだが、戦争でひともうけしようとした″死の商人″に踊らされた面もあったかもしれない。